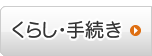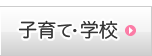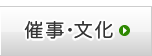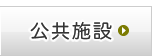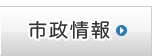退職金にかかる住民税の計算方法
更新日:2022年1月13日
退職所得にかかる住民税
個人市県民税は、納税義務者の前年中所得に基づき、その翌年に課税する仕組みになっていますが、退職所得については、原則として他の所得と分離して、退職手当等の支払われる際に個人市県民税を徴収することになっています。
よって、退職所得に対する個人市県民税は退職手当等の支払者が税額の計算をし、徴収したものを市に納付することになります。
計算方法
退職金にかかる住民税は、以下のように求めます。
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1※=退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
退職所得の金額×市民税率(6%)=市民税額(100円未満切捨て)
退職所得の金額×県民税率(4%)=県民税額(100円未満切捨て)
市民税額+県民税額=退職金にかかる住民税額(特別徴収すべき税額)
※(収入金額ー退職所得控除)した金額に対する2分の1控除が適用されない場合
- 役員等で、勤続年数が5年以下である場合
- 役員等以外で、勤続年数が5年以下の方の300万円を超える部分のある場合(令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等に適用)
退職所得控除
勤続年数に応じて、以下により計算した額を退職所得控除として退職金から控除することができます。
勤続年数の数え方は1年未満の端数を切り上げ、1年として計算します。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
- 退職金の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになって退職した場合
上記の計算で出た金額に100万円を加算した額が控除されます。