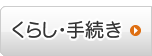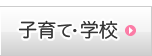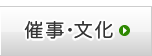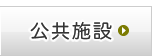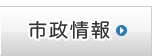パブリックコメント「第2次生涯学習推進計画」テキスト版資料02
更新日:2013年1月4日
第1章 第2次生涯学習推進計画策定にあたって
1 生涯学習の基本的な考え方
(1)生涯学習とは
生涯学習とは、一人ひとりが自己の充実と自らの生活の向上をめざし、自己に適した手段・方法で、生涯にわたって自発的に行っていく学習活動のことです。
こうした市民の学習活動は、個人の自己実現に止まらず、学んだ成果をボランティア活動など地域活動に生かすことによって、誰もが住みやすく安全で安心なまちづくりにつながっていき、地域、家庭、学校、職場が活気に満ちた社会になっていくものと考えます。
(2)生涯学習を取り巻く環境の変化
近年、パソコンやインターネット、携帯電話の普及による高度情報化、国際化、少子高齢化などにより、社会の情勢が目覚しく変化し、豊かで便利な社会になる一方、個人の価値観も多様化し、地域の人間関係が希薄な社会になってきました。
また、最近では特に、団塊世代の大量退職問題やフリーター・ニート問題への対応、子育てへの支援、家庭の教育力の低下等に対する対応が求められるようになりました。
市民の意識や行動は、「物の豊かさ」から「心の豊かさ」を志向するようになり、生涯学習活動も、それぞれのライフスタイルに合わせたものへと変わり、文化活動、地域活動から、ボランティア活動、スポーツ・レクリエーション活動に至るまで、さまざまな分野で学習活動への多様な取り組みがみられるようになりました。
2 生涯学習推進の取り組み
豊川市における生涯学習推進の具体的な取り組みは、平成2年度に開始されました。
当初は、身近な地域での学習機会を増やすことで、生涯学習の気運を高めていくことを目的に、市内6つの中学校区に生涯学習推進指導員を置き、学習ニーズの把握を主目的に市民アンケートを実施するとともに、生涯学習の推進に向けた構想や推進体制づくりについて検討を進めました。
平成3年度からは、全市的な推進体制の中核となる市生涯学習推進本部、市民代表や学識経験者から構成される生涯学習推進会議を設置するとともに、市内の公民館(4館)、市民館(22館)に1人ずつ生涯学習推進員を委嘱し、こうした施設を拠点にさまざまな講座や教室を開設するようになりました。
また、市民への情報提供を充実するため、市が取り組む年間の生涯学習関連事業を冊子にまとめ「生涯学習ガイドブック」として発行するなど、現在の取り組みのもとになる体制ができあがりました。
平成4年度には、生涯学習の気運を一層盛り上げるため、「生涯学習市民のつどい」を開催し、翌5年度には、市制施行50周年記念事業の一つとして「とよかわ生涯学習フェスティバル」を開催するなど、学習活動が暮らしの一部として親しまれるように取り組んできました。
その後、豊川市の生涯学習を総合的・計画的に推進するため、平成7年度に「生涯学習市民アンケート」を実施し、平成8年度には平成9年度から17年度を計画期間とする「豊川市生涯学習推進計画」を策定しました。
この計画に基づき、平成9年度には、市職員による推進体制を強化するため、生涯学習推進職員連絡会を設置し、全庁的に取り組み、平成10年度以降「生涯学習ガイドブック」の発行回数を増やすなどの充実や「地域生涯学習だより」、ホームページへの情報掲載、自主学習グループの調査や冊子「ハロー・サークル」の発行によるグループの紹介、「まちづくり出前講座」の実施などに取り組んできました。
平成13年度には「豊川市生涯学習推進計画」を一部見直し、改訂を行いましたが、社会情勢の変化や平成18年2月の宝飯郡一宮町との合併や第5次豊川市総合計画の策定等があり、こうした状況を踏まえ、今後10年間を見通した、「第2次豊川市生涯学習推進計画」を策定することといたしました。
3 豊川市における生涯学習の現状
(1)市民アンケートより
本市における生涯学習の現状について把握・分析し、第2次生涯学習推進計画を策定していくため、平成18年2月に実施しました「生涯学習に関する市民アンケート」の回答や意見・感想から次のような生涯学習に対する意識や現状、要望がうかがえます。
〇学習意欲は高いが学習活動に繋がっていない
生涯学習活動を大切だと感じている人は約8割と高い割合となっていますが、実際に生涯学習活動を行っている人は6割弱となっています。
〇学習する時間がない、学びたい講座がない
生涯学習を行っていない人の理由として、時間の余裕がないが半数を超え、続いて希望するものを学べる機会がない、何を学んでよいかわからないなどとなっています。
〇学習分野は健康、趣味、スポーツなどに関するものが多い
生涯学習を行っている人の学習分野は、健康、趣味、スポーツなどに関するものなど自己の健康維持向上や余暇時間の活用などが多くなっています。
その一方で、約1割強の人が身に付けた知識や技能を生かして、講師や指導等をしてみたいと考えています。
〇学習情報の提供方法の充実を求めている
市や民間などの講座、催し物などについて、市広報やガイドブックの掲載内容の充実やインターネット、ホームページなどを活用した情報提供を望んでいることがうかがえます。
〇学習ニーズが多様化している
近くの施設で、都合のよい時間帯に、たくさんのメニューの中から選択できる講座や教室を求めており、市民の学習ニーズが多様化等していることがうかがえます。
〇学習施設の充実を求めている
公民館、地区市民館などの身近な施設や、文化会館、勤労福祉会館、一宮生涯学習会館等の既存施設の改善を望んでいることがうかがえます。
※詳細は36ページ以降の生涯学習に関する市民アンケート報告書を参照
(2)前生涯学習推進計画の主要な施策の実施状況及び課題
これまでの生涯学習推進計画の中で示された主要な施策について、5つの分野に分け、主なものについて実施状況及び課題をまとめました。
学習機会の体系化
地域生涯学習事業
生涯学習指導員・推進員を中心に公民館や市民館での身近な学習の場の充実に取り組んできました。その結果、各地域で数多くの生涯学習講座が開催されています。しかし、開催される講座の内容に固定化の傾向が見受けられることや講座数の拡充に限界があることなど、問題点もみられます。
学校開放講座
小中学校の施設や機能、地域の人材、教育力を活用した講座の開催を目標にして取り組んできました。
その結果、体育館や運動場などの体育施設についての学校開放は進み、地域で活用されています。しかし、コンピューター室等の開放はセキュリティーの確保等、施設の管理面に課題があり、関係者との調整を行う必要があります。
まちづくり出前講座
市民の知りたい情報について市職員を派遣する出前講座については、老人クラブ等の団体を中心に利用が定着しています。今後は、提供するメニューの多様化や市職員以外の講師の派遣についても、要望があれば派遣できる体制をつくるなどの必要があります。
新・市民大学構想
企画運営面における市民参画を前提にした、市民と行政の協働による開かれた市民大学を目標に取り組んできました。その結果、総合講座、専門講座に分け、企画運営ボランティアの参加を得て開催されるようになりました。
今後は、総合講座の著名人を招いての講演会形式ばかりでなく、専門講座を中心として、少人数で専門的な講座の種類を増やしていくことや市民・NPOなどが主体的に参画し、行政と協働できるシステムを作っていく必要があります。
人材の養成と活用
指導者の発掘・活用
平成15年度から生涯学習支援ボランティアバンク制度を創設しました。現在97個人、20団体の登録がされていますが、利用率は低いものとなっており、制度のPR等を積極的に行い、活用を促進していく必要があります。
ジュニアリーダー
わくわく体験ランド等を通じて、地域の子どもたちの中心となって活動できる中学生・高校生のリーダーを育成することを目標に取り組んできました。
その結果、平成15年度に市子ども会連絡協議会の中にジュニアリーダー部会を設け、育成にあたっています。今後はより一層ジュニアリーダーの養成に力を入れ、次代を担う人材の育成を図る必要があります。
生涯学習推進員
地域生涯学習講座の企画運営を行っていく地域のボランティアとして、現在29名が活動しています。
今後さらに地域生涯学習講座を活性化していくため、研修制度の充実や生涯学習推進員の公募制等を検討していく必要があります。
学習関連施設の整備
公民館や地区市民館
建設されてから年数が経過してきており、必要な修繕については計画的に進められてきました。今後も引き続き施設の充実を図っていく必要があります。
児童館
当面、中学校区に1館を目標に、平成13年度に「さくらぎ児童館」、平成15年度に「うしくぼ児童館」、平成17年度には「さんぞうご児童館」を整備しました。現在、7中学校区中5中学校区に児童館がありますが、今後は、児童館がない中部中学校区と西部中学校区に児童館を整備する必要があります。
中央図書館・ジオスペース館
平成11年7月に中央図書館・ジオスペース館が開館し、図書資料やプラネタリウム番組などの生涯学習機能が充実されました。今後は中央図書館を核とした、市域内における図書館分館機能の構築等に関する検討が必要になります。
赤塚山公園等
ぎょぎょランド、アニアニまある、昆虫の森などの施設整備を平成15年度までに完了し、自然と親しみながら三世代が憩い学習できる施設として活用されています。
史跡公園
平成17年11月に国分尼寺跡史跡公園がオープンし、「三河天平の里資料館」では歴史講座や体験教室を開催するなど、豊川市の歴史を学ぶ学習施設として活用されています。
生涯学習センター構想
生涯学習の拠点としての生涯学習センター構想は、財政事情や社会情勢の変化により、進展していない状況です。生涯学習の拠点施設の整備については、既存施設の活用等を考慮しながら検討していく必要があります。
野外活動施設
きららの里を平成12年7月に整備しました。小学生や一般市民を中心として、野外学習活動の場として活用されています。
学習情報システムの整備
学習相談窓口の充実
地域の学習相談窓口として、7中学校区の公民館等に配置した生涯学習指導員が対応しています。今後は、多様なニーズや専門的な相談に対応できるよう体制を充実させていく必要があります。
地域生涯学習だより
中学校区ごとに地域生涯学習講座の情報を、年2回発行し、公民館を中心とした公共施設の窓口やロビーに置くなどして情報提供しています。今後は全戸配布やホームページへの掲載等、より広く周知していく必要があります。
市広報・ホームページ
ホームページ等のIT情報の活用については、高齢になるほど進んでないと思われるため、今後はホームページへの掲載情報の充実に加え、高齢者に対するITを活用するための教室や講座などを充実させていく必要があります。
生涯学習ガイドブック
現在年2回、2,500部を発行し、内容についてはホームページへも掲載しています。他市町村の情報等も掲載し、情報量は多くなっていますが、今後、全戸配布や設置・配布場所等を検討し、広く周知する方法などを検討していく必要があります。
学習情報のネットワーク化
第1段階として情報収集・提供の一元化、第2段階として情報通信システムの導入の2段階で情報ネットワークを構築することとしています。現在は、まだ第1段階でありますが、平成18年度に、体育施設利用申込のオンライン化が一部開始されました。公民館等のIT関連機器の整備や利用申込のオンライン化が今後の課題となっています。
生涯学習推進体制の整備・充実
青少年健全育成
家庭、地域、学校及び関係者が一体となって、青少年健全育成を推進するものであり、全ての小学校区で青少年健全育成推進協議会が組織され、様々な取り組みがされています。
今後も、関係機関と連携を図りながら、地域の実情にあった活動をしていく必要があります。
青少年の体験学習機会
子どもセンター協議会を組織し、小学生を対象とした「子どもものづくり教室」、「親子ふれあい工房」、子どもの居場所づくり事業である「土曜教室」等が行われています。またキャンプ体験を中心とした「わくわく体験ランド」事業も展開されています。
これからの教室等の開催にあたっては、参加者の要望を把握したうえで、体験学習の機会を充実させていく必要があります。
国際交流のネットワーク化
外国人との国際交流活動は、国際交流協会を中心に進められてきました。その一方、外国人の増加、愛知万博の開催、中部国際空港の開港など、内外を問わず国際化が加速する中で、外国人向けの日本語学習機会の充実や、広く市民を対象とした異文化理解、多文化共生などをテーマとする講座等の充実、海外各都市との市民間交流や協力など新しい取り組みも必要となってきています。
情報収集の広域的連携
東三河の市町村が連携し「東三河連携講座」が開催されています。また、「生涯学習ガイドブック」に東三河市町村の生涯学習情報を掲載しています。
今後とも、情報の共有化や事業の連携を積極的に図る必要があります。
(3)生涯学習推進計画に基づく施策の進捗状況
上記(2)で記述した内容も含めて、「生涯学習推進計画に基づく施策の進捗状況」及び「市域生涯学習事業実施状況」(平成17年度実績)として現在までの取り組みを整理しました。